ラバナスタからアルケイディスに引き戻されたヴェインは父グラミスと密談をしていた。
「奴らを抑える口実が必要です」
ヴェインは長いアルケイディスの歴史の中で元老院たちがどれほどソリドール家の栄光を憎み、その命脈の息の根を止めようと手段を選ばずに来たかをよく理解していた。例え自分が失脚しようと、その程度の事でソリドール家の安泰が約束されるとはとても思えなかった。相手がソリドール家を潰そうとしているのなら、逆にこちらで元老院を潰す手段を考えればよい。その手段としてヴェインは皇帝グラミスに「死」という口実を迫っていた。
「口実が必要だと?そうか、必要か・・・・。そちの決まり文句だな。血を流す決断に毛ほどのためらいもない」ゾッとしながらグラミスが言った。
「・・・ソリドールの剣に迷いは不要。その剣を鍛え上げたのは陛下ご自身です」
「・・・・復讐のつもりか」グラミスは11年前に自分が息子にさせた事を思い返していた。彼にとっての実兄たちを殺せと命令したのは、グラミス本人だ。ヴェインがそれをどうとらえたかはわからない。しかし彼の血塗られた人生はそこから始まっている。彼の母親は、その事実を知り、あまりのショックと心痛でこの世を去ってしまった。そういった人生を背負わせてしまったこの父をヴェインは憎み、復讐しようとしている。
グラミスはそう解釈していたわけで、今にも自分が殺されるのではないかと、恐る恐る息子の冷たい横顔を見た。
「・・・・復讐ではありません。口実が必要だと申し上げただけです」ヴェインはそんな父親の心中を悟ってか、あっさりと言葉をかわし「今やらねば、もう一人の未来も奪われます」と答えた。
「 白い手の者にかわり、その手を汚すか」グラミスはヴェインがラーサーの事を言っている事を理解した。仮にヴェインが失脚し、グラミスが病死し、ラーサーが次期皇帝になったとして、わずか12歳の彼は、たった一人で元老院たちに立ち向かわなければならない。おそらく元老院たちは、ラーサーが自分たちの人形に出来ない器の持ち主である事に気づきはじめている。それが決定的になった時、元老院たちはラーサーをも潰しにかかり、ソリドール家の命脈は絶たれてしまうだろう。
「その手を汚す」父親の言葉にヴェインは冷たい口調で答えた。「私の手は、すでに血で染まっています。ならば最後まで私が」
ヴェインは父の命令により、兄2人を殺した。今更その手が血で汚れる事などヴェインにとってはどうってことない事なのかもしれない。グラミスは覚悟したように、深いため息をついた。
いずれにしても、自分の老い先はもう長くはない。死病は日に日に体を蝕んでいる。自分の死を惜しむよりは・・・・
「全てはソリドールのために・・・・」グラミスは自分に言い聞かせるように呟いた。
それから間もなく、皇帝グラミスは元老院グロゴロス議長を首謀者として暗殺された。グロゴロスは皇帝に毒を盛った事を認め、潔く自決し、グロゴロスの共犯者として名前のあげられた元老院たちはすべて捕らえられてしまった。
「自決だと?たわごとを!!私が真の反逆者を見抜けんと思うのか!?」
ドレイスはグラミスを暗殺したのはヴェインであると確信していた。 自分の権力のためなら親をも殺す、その非情さに耐えられなくなって、ヴェインに押し迫った。
「言葉がすぎるぞ、ドレイス」そんなドレイスをたしなめるような口調でザルガバースが非難した。
「ザルガバース!卿までもが茶番を演じるのか!?」怒り収まらぬドレイスはなおも感情的にザルガバースに反抗した。
「・・・ロザリアの侵略が迫る今は、ヴェイン殿の力が必要だ」ザルガバースが仕方なさそうにそう言った。
「・・・・ソリドール家も、私とラーサーを残すのみになった」そんなドレイスの怒りをあおるようにヴェインが言葉を挟んで来た。
ドレイスは、ラーサー、という言葉に敏感に反応し「まさかラーサー様をも・・・・!?ヴェイン・ソリドール!法の番人たるジャッジ・マスターとして、貴殿を拘禁させて頂く」そう言って、幼いラーサーをも暗殺しようと言わんばかりのヴェインについに刃を向けたドレイスに、逆にベルガが剣を突きつけて来た。ドレイスは、鋭い刃を背中に感じ、思わず息をのんだ。
「ヴェイン閣下を独裁官に指名したのは、法を司る公安総局だ。わかるか?ドレイス。閣下に剣を向けた瞬間、おまえは法に背いた」
日頃よりアルケイディスでは議会制を重んじ皇帝をも選挙で選ぶ。しかし戦時中など、緊急時には特定の人物に独裁官としてすべてをゆだねる習慣があった。今回皇帝暗殺という非常事態に陥り、その上に、皇帝暗殺の首謀者である元老院の権限が凍結された今、次回の選挙までつなぎ止めるという形で ヴェインが権力を一手に握ることになってしまったのだ。また、ベルガの言う法を司る公安総局とは、いわゆる司法局で、ジャッジ隊の正式名所でもあった。この組織はジャッジ・マスターたちの力関係をもとにして 合議や駆け引きで運営されていた。その公安総局に刃向かったドレイスはジャッジ・マスターとして謀反を働いた事になり、罰されて当然だったのだ。
「貴様も茶番の共犯か!!」
カッとしたドレイスは、振り向き様にベルガを斬りつけようとしたが、逆に頭を鷲づかみにされ、そのまま投げ飛ばされた。あまりの衝撃と痛みにドレイスは気が遠のきそうになり、人間の者とは思えぬ異様な力に恐れおののいていた。
「ザルガバース。アレキサンダーを与える。ベルガを伴ってラーサーを連れ戻せ」ザルガバースに向かってヴェインが言った。 ザルガバースは「はっ」と言ってうやうやしく頭を下げた。
その様子を見つめていたガブラスは 「閣下、ラーサー殿の保護は私が」 と、平静を装うようにして言った。しかしヴェインはそんなガブラスを見透かすように「私を監視しなくてもいいのか?あれこれと探りを入れて、グラミス陛下に報告していたそうだが?」と言った。
ガブラスは言葉を失い、自分の身の危険をとっさに察知した。
「殿は陛下の犬だった。いまさら飼い主を変えるつもりなら・・・・」ヴェインはそう続けて、息絶え絶えになっているドレイスに目を向けた。「そうだな、ジャッジ・マスターの職務を全うしてみせろ。法に背いた者を裁け!」
「閣下!それはあまりに!」まだその場所に残っていたザルガバースが叫んだ。しかしガブラスは、ドレイスの剣を取って彼女の胸元に突きつけた。
ドレイスの意識は、もう、はっきりはしていなかった。しかし、彼女は最後の力を振り絞って、ためらうガブラスに向かい、静かに言った。
「かまわん・・・・やれ。 ・・・・生き延びて、ラーサー様を守って・・・・」
ガブラスにとって彼女を殺す事は、自分がヴェインに殺されずに済む事。ドレイス自身がそれを望んでいる事が、どういうことなのか ガブラスはこの時、はっきりとわかった。
生き延びて、ラーサーを守り抜くために自分はここにいる。いつか誓ったドレイスとの約束を守ろう。それが、彼女へのせめてもの償い・・・・
ガブラスは、ザルガバースがドレイスをかばい、彼の立場も悪くする事を避け 一気に剣をドレイスの胸に深く突き刺した。ドレイスはカッと目を見開き、絶命した。
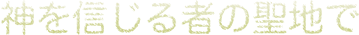

 戦乱の幕開け
戦乱の幕開け ファイナルファンタジー12
ファイナルファンタジー12 汚れた血
汚れた血
