ドクター・シドの言葉が本当ならば、ギルヴェガンで破魔石を授かる可能性がある。暁の断片が使いものにならないのなら、その新たに授かる破魔石でダルマスカを再興すれば良い。一方で、ミリアム遺跡で入手した覇王の剣で破魔石を打ち砕こうとしている自分もいる。どちらを選択するのか答えが出せぬまま、アーシェは憂鬱な思いでギルヴェガンの奥地を進んでいた。
数えきれぬほどの転移装置を使い、異空間に飛ばされてきた彼らだったが、ある瞬間、アーシェだけが彼らとは別の空間に飛ばされてしまった。
一瞬、気が遠くなり、ほどなくしてたどり着いた先は、眩しいくらい白くて大きな天空の円卓のようだった。
アーシェは驚いて、仲間の名を呼んだが、シンと静まり返るだけで、なんの返事はなかった。
彼女は恐れおののき、呆然と立ち尽くしていると、どこからか、低い声が聞こえて来た。
「恐れるな、ダルマスカの王女よ。我らオキューリアはそなたのみを選んだ」
アーシェは声が聞こえて来る方向に振り返った。
揺らめく影のようにミストがざわめき、やがて、オキューリアの族長、ゲルン王が彼女の前に姿を現した。
オキューリア族は、創世記から既に何万年も生き続けており、自分たちの代行者を他種族から選んで 破魔石を授けてきた。
まるで神のように人間の歴史を動かしてきたオキューリアを、ヒュム族は「不滅なるもの」と呼んで、崇めてきた。
「アーシェ・バナルガン・ダルマスカよ」ゲルン王は、もう一度アーシェの名前を呼んだ。「力を求めるそなたの心、我らが聖なる力へ導く。絶海の塔に眠る『天陽の繭」を求めよ」
天陽の繭・・・?アーシェは心の中で呟いた。
「天陽の繭は全ての破魔石の母、力の源。覇王の遺産など、繭から切り取られた欠片にすぎん」
「あれほどの力が?!」アーシェは驚嘆した。
「往古、我らはイヴァリースを救うべく、レイスウォールを選んで剣を授けた。 王は剣で繭を刻み、3つの破魔石を得て覇王となった。 その血を継ぐ者よ。父祖と同じ道を歩め」
「覇王の剣は、そのために・・・」ゲルン王から聞かされた真実に、アーシェはさらに驚嘆していた。
「レイスウォールとの古き契約は、とうに力を失った」
破魔石を入手するには天陽の繭の封印を解かなければならない。封印を解き、はじめて石を刻めるのだが、これは神なる存在,オキューリアから選ばれし者のみが 己の契約の際に授かった剣を用いて、初めて実行可能だった。つまり、オキューリアと直接契約していないアーシェが、他人(レイスウォール王)に授けられた剣を用いても破魔石は得られない、ということなのだ。今や、レイスウォールはこの世に存在しておらず、今、アーシェが所持している契約の剣は 持ち主をなくし、力を失っている剣にすぎない。
「そなたとは新しい契約を結ぼう」ゲルン王がそう言うと、アーシェの前に剣が現れた。「我らオキューリアの代行者たる証に、新たな剣を授ける。『天陽の繭』を切り取って 破魔石を掴むのだ。覇王と同じ力を手にし、ヴェーネスを討て」
「・・・ヴェーネス・・・・あなた方と同じ、オキューリアですね」
「異端者だ!!」ゲルン王の激しい怒りのミストが辺りに嵐のように立ちこめた。その怒りのミストにアーシェは圧倒されそうになったが、円卓に備えられたそれぞれの台座にオキューリア達が姿を現した。「破魔石は我らに選ばれし者のみが手にすべき力。だがヴェーネスは人間に破魔石の秘密を教え、まがいものを作らせている! 偽りの破魔石を掲げる者どもを許してはならぬ。我らが授ける真の破魔石をもって、滅亡の罰を!」
「滅亡?」そう問いかけたアーシェの前に、ラスラの幻影が現れた。アーシェはラスラに向かってもう一度問いかけた。「帝国を滅ぼせと?」
ラスラは、大きく首を縦に振って、肯定の意を示した。
戸惑うアーシェに向かって、ゲルン王はなおも続けた。
「人の子は、常に歴史を狂わせる。短すぎる人生に焦り、くだらぬ欲望にかられ、あやまちを重ねつつ滅びへとひた走るばかりよ。 我ら不滅のオキューリアが無知なる人の子を導き、時には罰を下してこなければ・・・ イヴァリースはとうに滅びて来た。我ら、不滅なるものには、正しき歴史を定める義務がある。我らに選ばれし者には、正き歴史に逆らうものに、罰を下す義務がある。
王女よ。そなたは選ばれたのだ。国を奪った者どもに復讐を遂げ、救国の聖女となれ」
ラスラの幻は、アーシェに剣の柄を握るように促した。 アーシェは、剣に手を伸ばした。
「選ばれし者の義務を果たせ」
アーシェの脳裏にゲルン王の声が低く響いた後、彼女はやっと仲間のいる場所へ戻された。
アーシェは、まだ、意識だけがどこかに飛ばされたままだった。
しかし、ゲルン王の声は仲間達には届いていたのだ。ヴァンは、戻ってきたアーシェに興奮して話しかけた。
「アーシェ!なんなんだよ、オキューリアって、わけのわかんない命令ばっかでさ!」
「言われた通り、復讐するの?」フランが、そう訪ねて、「復讐」という言葉に敏感に反応したアーシェはようやく意識も 仲間の元へ戻ることができ、え?、とフランの顔を見つめた。
訳のわからぬ様子のアーシェにバッシュは状況を説明しはじめた。
「我々にも、声だけは届いておりました。彼らは神にも等しい存在かもしれませんが・・・殿下、私は反対です。帝国と言えども、滅ぼすなど・・・・」
バッシュの言葉に、アーシェは目を反らした。
「あの・・・」先ほどから、ずっと気になっていたのか、パンネロが恐る恐る、話しはじめた。「ドクター・シドはどうなったんでしょう?ここに来るって言ってたのに」
「たしかに遅すぎるな」
「ああ」バッシュの言葉に納得するようにバルフレアが頷き「気づくのが、遅すぎた。奴は来ない。オレたちは引っかかったんだ」そう言って、目を伏せるアーシェに向き直った。「ドラクロアを思いだせ。アーシェに石を手に入れさせたい、そんな口調だったろ。 だから、破魔石を見せびらかし、ギルヴェガンの話でオレたちを呼び寄せて・・・ アーシェとオキューリアが会うように仕向けた」
「でも、私たちが破魔石を手に入れたら、帝国の邪魔になりますよね」パンネロが率直な疑問をバルフレアに投げかけた。
「破魔石同士がぶつかるのを見たいんじゃないのか?アイツの考えそうな事だ」
苛立った様子のバルフレアに対して言ったのか、仲間に言ったのかはわからなかったが、アーシェはきっと顔を上げ「『天陽の繭』を探すわ」と、歩き出した。
シドのようにアーシェの心も石に奪われてしまう事を恐れていたバルフレアは、 わざと彼女に聞こえるように大きな声で言った。「歴史は人間が築くもの・・・あいつの持論だ。オキューリアの石で動く歴史なんて、あいつには我慢できないはずだ」同時にバルフレアは、現れなかった父を思った。「あいつ、ずっとヴェーネスと話してたんだな。 おかしくなったんじゃ、なかったんだ・・・」と、父が正気であったことに安堵もしていた。
「『天陽の繭』は絶海の塔に眠るというが、心当たりは?」バッシュは、なんでも知っていそうなフランに訪ねてみたが、彼女にも見当がつかぬようだった。
「レダスに聞いてみようよ。あいつ、他の線とかなんとか言ってたぞ」
「奴に借りを作るのはどうもな」ヴァンの提案に、気の進まない様子でバルフレアは答えた。
「何こだわってんだ?空賊同士、仲良くしろよ」
無邪気なヴァンには、バルフレアがシドとレダスの関係を疑って協力の要請に躊躇している事など気づくはずもなかった。 単にバルフレアがレダスに対し、意固地になってるとしか思えなかったのだ。
嫌味ない彼の言葉に、バルフレアのわだかまりが少し軽くなった。
しかし、バルフレア風の言い回しで「お説教とは偉くなったもんだな、ええ?」と、ヴァンの成長ぶりをからかった。
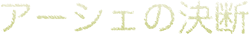

 戦乱の幕開け
戦乱の幕開け ファイナルファンタジー12
ファイナルファンタジー12 神々との契約
神々との契約
