天陽の繭は裂け、跡形もなく吹き飛んだリドルアナ大灯台の頂上とともに神授の破魔石は消失した。シュトラールは危機一髪で塔を脱出し、バーフォンハイムに到着していた。
エアターミナルにシュトラールを停め、ヴァンたちが港町を歩いていると、レダスの部下リッキーが、レダス邸に客が来ているので会ってほしい、とヴァンに駆け寄って来た。客人とは一体誰なのだろう、リッキーに導かれて一行はレダス邸に入った。
「アルシド?」思わずヴァンが言った。
相変わらずの気障な振る舞いで、机の上に大きく足を投げ出したアルシドの姿が一行の視界に飛び込んで来た。ヴァンの呼びかけでアルシドはサ立ち上がり、彼らを歓迎した。「上がらせてもらってますよ。いささか急を要する状況ってことで」
「なんでオレたちの居場所が?」ヴァンが目を白黒させながら訪ねた。
「うちの情報部はきわめて優秀でして」アルシドはそう答え、アーシェの側に歩み寄った。「姫・・・・戦争が始まります」
「・・・ロザリア軍を、止められなかったのですか?」アーシェは息をのんだ。
「少々汚い手を使って、強硬派の将軍連中に引退願うまではうまくいったんですがね・・・大本営の参謀ども、裏から手を回していたんですよ。 オンドール公爵の解放軍です」
「解放軍が!?」アーシェの表情が険しくなった。
「解放艦隊の一部が、訓練中に命令を無視して離脱・・・。旧ナブラディア空域で帝国軍と交戦状態に入りました」
「なぜ、わざわざ見つかるような真似を!」バッシュが苛立って言った。
「そいつらロザリアからの舞台だったんですよ。義勇部隊だか、傭兵って建前で、解放軍に加わってたが・・・・正体は大本営直属のロザリア正規軍ときた」
少し前からオンドール候の解放軍には、義勇部隊と称してロザリア軍が参加していた。 戦力をわけ与えれば解放軍がアルケイディア軍に宣戦するだろうから、そうなったら両方の戦力が減るのを待ち、 解放軍が公に支援を求めて来たところで堂々と参戦・・・というのが、ロザリア帝国の計画だったのだ。 だが、オンドール候は交渉狙いで動かないため、ロザリア帝国は解放軍にもぐりこませていた自国の軍を動かし 開戦の口火を切ったとアルシドは言い、「・・・解放軍は見捨てるわけにもいかず、オンドール公爵閣下は、やむなく主力艦隊に出撃を命じました。・・・・・・戦場はダルマスカです」
アーシェの表情がますます険しくなった。そんなアーシェを気にしながら、バルフレアが訪ねた。
「解放軍と帝国軍の戦いが泥沼化したら・・・ダルマスカ保護を口実にロザリアも参戦だな?」
「そう、おいしいところをかすめ取るつもりでノコノコ出てったラザリア軍は・・・・解放軍ともどもヴェインに叩き潰されますな」
「・・・・ヴェインは『黄昏の破片』を失ったはずだ。切り札はないはずだ」我が身を犠牲にし天陽の繭の砕いたレダスを思い、バッシュが冷静に言った。
「・・・別の切り札があったんですよ。うちの情報部が大物の稼働を確認しましてね」アルシドはそう答えて、改めてアーシェに向き直った。「空中要塞、バハムート。リドルアナの方向で異常なミストの反応があった直後のおめざめってわけで」
彼の言葉を聞き、フランが直感的な推測を述べはじめた。「『天陽の繭』の暴走であふれたミストが、バハムートの動力になったんだわ。 レダスが繭を止めていなければ、数千倍のミストを吸収していたはず・・・・」
バハムートは、従来の戦艦とちがって人造破魔石を搭載している。この石は天陽の繭の膨大なミストを取り入れてる上、「魔力を周囲から取り込む」という破魔石特有の性質を持つため、バハムートは恐るべき力を半永久的に使用可能となっていた。
フランはバルフレアを見つめ、言葉を足した。「それが、ドクター・シドの計画だったのね」
「あいつの最後の仕事ってか・・・ オレの仕事は、その後始末だな」
バルフレアは、このとき、自分の死を覚悟していた。 父親シドの罪を、自分が償う。そのために、バルフレアは、バハムートを破壊するのは自分の使命だと思っていた。しかし、この時のアーシェには、その言葉の意味に気づけなかった。
「ヴェイン、自らバハムートからダルマスカへ?」
「来ますよ、ダルマスカへ」
アルシドの答えを聞き、アーシェは意を決するように閉じていた目を見開いた。「・・・・バハムートを止めて、ダルマスカを守る。それが私の・・・・」
「オレたちの仕事だ!」ヴァンがアーシェの言葉を打ち消すように元気よく言った。
「私たちの街を守りましょう!」続いてパンネロが言い、アーシェの手を握った。
アーシェは感慨深く、微笑んだ。今まで苦労を共にして来た、仲間への強い絆が、心の中に芽生えているのを感じた。もう、1人ではない。そう思えたアーシェの表情が、仲間にはとても美しく、輝いて見えた。
そんなアーシェに見惚れながら、アルシドが言葉を続けた。「だったら、出来るだけロザリア軍の侵攻を遅らせるのが私の仕事ですかね。 まぁ、やってみましょう」そう言って、立ち去ろうとしたが、ああ、と思いだしたようにアーシェの元へ戻ってきた。そして、彼女の前に跪き、これまでの戦いで傷だらけの王女の手を、大切そうに握った。
その情熱的な振る舞いに、アーシェに変わりパンネロが顔を赤らめ、バルフレアが、面白くなさそうな顔をした。
「・・・面倒が片付いたら、一度ロザリアへおいでください。我がマルガラス家発祥の地・・・夕日にきらめく”琥珀の谷”をご案内しましょう」そう言って、アルシドはアーシェの前を去った。
まんざらでもなさそうなアーシェの表情に、この物語の主人公を気取るバルフレアには、すっかり主役の座を奪われたようで、ますます面白くなさそうだった。
その頃ラバナスタの上空では、バハムートのコントロールルームでヴェインがシドの死因について、ヴェーネスから報告を受けているところだった。
シドが実の息子バルフレアによって命を絶たれた事など、ヴェインにとってはなんら、珍しい事ではなかった。自分が父グラミスに死を迫った過去への自嘲的な感慨が含まれていたからだ。ヴェインは情の欠片もない冷たい表情で解放軍に狙いを定めるよう、帝国兵たちに指示を出した。
「目標、反乱軍重巡!」ヴェインの側で指揮をとるジャッジが言った。 帝国兵達が次々に指標を定める。「発射緒元、解析完了。照準よし」
「おやめください!彼らは降伏したんです!」軟禁され、自由を奪われ、発言すら無視されて来たラーサーが、いたたまれなくなってコントロールルームへ入って来た。
「シドへのせめてもの手向けだ。あの世からも見えるだろう。なぁ、ヴェーネス」ヴェインはそう言うと、指揮官に向かって合図した。「主砲射撃準備完了!」
「兄上!」ラーサーの言葉も空しく、ヴェインが「撃て」と声を出すと、解放軍の艦艇はバハムートの砲撃に沈んでいった。
あまりのショックにラーサーは目眩を起こし、その場に倒れそうになった。「・・・・なぜ・・・」
「降伏しても無駄と知れば、反乱軍はこの戦いに全てを懸ける。 ・・・それを正面からたたき潰す。ラバナスタの目の前でな」
冷たくそう言い放つ兄に幻滅し、ラーサーは力なく言葉を返した。「・・・・それでは、人々が兄上を憎むだけです」
「許しても再び反乱軍を企む」
「僕はそう思いません!」ラーサーの声が、再び力を取り戻した。「手を取り合う未来を信じます。 あなたは・・・・ あなたは、間違っている!!!」
自分に比べればとうていなんの力も持たない、まだとても幼い弟を見つめるヴェインは、嘲笑するような口調で答えた。「・・・・ならば、私を正す力を身につけるのだな」
ラーサーは、グッと言葉につまった。
「聞け!」そうしてヴェインは声を張り上げた。「われらが築く歴史の第一歩である!各員その義務を果たし、反乱軍を攻撃せよ!アルケイディス万歳!」
一同が、まるで神に祈るような声で 「アルケイディス万歳!」 と唱和していた。
ラーサーは耐えられなくなって、コントロールルームを後にした。
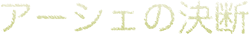

 戦乱の幕開け
戦乱の幕開け ファイナルファンタジー12
ファイナルファンタジー12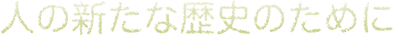
 空中要塞バハムート
空中要塞バハムート
