ブルオミシェイスからガブラスによってアルケイディスに連れ戻されたラーサーは、これ以上に1人で勝手な行動をおこさぬようにと、兄ヴェインによって監視され、終始軟禁されていた。ラーサーはそんなヴェインに和平への自分の思いのたけを訴えていた。
「アーシェ王女と和解し、ダルマスカの独立を認めるべきです。大戦を防ぐには、それしか」
ヴェインは幼い弟の言う事に耳もかさぬ様子で「必要な戦いだ」と答え、戦争の道を歩むのも世を平定するための最善の策と、そこに情の介在する余地もなかった。
「・・・そもそも彼女こそ、心から戦いを望んでいる。我が国への、復讐をな」これまでアーシェが破魔石の「力」を求めるあまり、ヴェインには彼女にそのような印象しか持っていなかった。
「僕は違うと思います。アーシェさんはそんな人じゃない」
「幼いな」
ヴェインに自分の幼さを指摘され、ラーサーはますます熱くなった。「どうして決めつけるんですか?!」
「ならば、ガブラス」ヴァインは後ろにいるガブラスを呼び寄せた。「卿が見極めろ。アーシェ王女が求めるものが、平和か、あるいは戦争か。その目で確かめて来い」
「我が国への復讐を望むなら斬る・・・・それでよろしゅうございますか?」ヴェインの命令に対し、ガブラスは問うた。 しかし、ヴェインが答える前にラーサーがガブラスをまっすぐに見つめ、答えた。
「・・・僕はあの人を信じている。それにガブラス、卿の目も。卿に賭けたい。卿を信じる」ラーサーの言葉には飾り気がなかった。子供ゆえの、純真な信頼を思いきりガブラスにぶつけた。
ガブラスにとっては、これまでのラーサーの護衛はグラミスや、亡きドレイスの意向に応えるための義務でしかなかった。 しかしこのラーサーの純真な信頼は、騎士としてのガブラスの忠誠心を強く刺激していた。
「・・・御意」ガブラスは頭を下げ、ラーサーとともに部屋を出て行った。
その姿を見届けると、先ほどから隣の部屋でヴェインとラーサーのやりとりを見ていたシドが側に寄って来た。「あんたの弟とは思えん甘さだな」
シドの言葉にヴェインは苦笑を浮かべ「・・・ラーサーはあれでよい」と応えた。
しばらくして、シドが何かを感知したように、宙に向かって話しはじめた。「ん、どうしたヴェーネス?」
ヴェインも注意深く、シドを見つめた。
「・・・ほう、餌にかかったか。早いな・・・」そうしてシドはヴェインに目を移し「王女がオキューリアの剣を授かった」
「・・・・不滅の神々が神々が導きたもう、正き歴史を守る聖女。その手には新たな破魔石か・・・」ヴェインの言葉にシドは、フン、と鼻を鳴らして言った。
「オキューリアの石など!馬鹿力だけでろくに制御できん出来損ないだ。所詮、実験材料にすぎん」
シドは、これまでの事例、夜光の破片を実験台にしてナブディスを壊滅させてしまった事、 暁の断片により、リヴァイアサンを撃沈させてしまった事、 人間の力ではコントロール不能な、所詮役立たずの破魔石をそのような言葉で表現した。
「あれのために国ふたつ攻めたぞ」シドの言葉にヴェインが再び苦笑した。
「ああ、犠牲には感謝しとるよ。おかげで人造破魔石が完成した。優秀で確実な兵器だ。・・・なぁ、ヴェーネス。わしはなかなかの弟子だろう?」人造破魔石の利点は、誰でもその力を意図した通りに引き出せる点にあった。コントロールが利かず、国を壊滅させてしまうほどの力がある神授の破魔石とちがい、 力を欲する人間にとっては、非常に扱いやすい兵器なのである。シドに話しかけられ、ヴェーネスがようやく姿を現した。
「・・・私は助言を与えたにすぎない。あれを完成させたのは、君たち人間の力だ。素晴らしいものだ、わずか6年で。 人間の情熱は想像も不可能も超えて進む」
「人生は短いんでな」シドはヴェーネスの言葉に得々と答えた。「あんたら不滅の存在と違って、もたもた出来んのよ」
「ああ。踏みつぶしても進まなければ、何も成し遂げられなかった」シドの言葉に補足するようにヴェインが言った。
「あんたの仕事はこれからだ。神を気取るオキューリアの意思を超えて歴史を人間の手に取り戻せ」そんなヴェインにシドはエールを送った。
『歴史を人間の手に取り戻せ』
その言葉を口癖のようにたびたび口にするシドに対し、ヴェーネスが言った。「そうだ。ギルヴェガンにこもって不滅の時に停滞するゲルン王は・・・・歴史を導く資格などない」
ヴェーネスは、他人に指図するだけでギルヴェガンに閉じこもり、悠久の時を過ごすゲルン王たちに疑問を抱いていた。そんなヴェーネスにとって人間は、限られた時間しか生きられないながらもオキューリア族がとうに失った情熱を持つ、という点で 興味と羨望の対象だった。この6年で人間に愛着を抱くようにもなり、とくにシドと、シドが覇王の器と見込んだヴェインとは、 同志とも友人とも言える絆を抱いていた。
「ヴェイン。君のために祈ろう。高みへ辿り着くように」
シドとヴェーネスのエールに、ヴェインはいささか重苦しい表情をし「たどりつくさ・・・この私にふさわしい場所へな」そう言って、自分が辿って来た血塗られた人生を振り返った。
尊い命を血に汚して来た自分の未来には、多分、それに見合ったふさわしい末路が別にある、と。
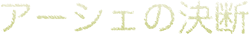

 戦乱の幕開け
戦乱の幕開け ファイナルファンタジー12
ファイナルファンタジー12 異端者ヴェーネス
異端者ヴェーネス
