バハムートからの砲撃を受け、解放軍主力艦は一瞬で打ち砕かれた。
旗艦ガーランドで指揮をとるオンドールはその様子に目を背けながらも次の部隊を出陣させていた。
「諸君!生きて返るぞ!」
それでもバハムート起動前までは、両軍互角の戦いを続けていた。
「全門斉発、撃ち方はじめ!」
「射線、開きます!」
「第2斉射、急げ!」
解放軍の艦載艇が、第一波攻撃を終えて退避し、第二波攻撃を開始しようとした時、バハムートの主砲にエネルギーが充填され行くのが確認できた。
ついにバハムートが起動した瞬間だった。オンドールは今まで見たことのないような主砲口の大きな面積に圧倒された。あれで砲撃を受けたら・・・・
「いかん!」
オンドールが立ち上がった時は、もう、遅かった。ものすごい勢いと速さでバハムートから主砲が放たれ、解放艦隊の空母があっという間に撃沈されてしまった。
「空母がラフ・バル、轟沈・・・・」無念の意が伺える解放軍の声が通信機から聞こえ、オンドールの目の前で、空母は無惨に墜ちていった。
自分の命運もここまでか、とオンドールが観念したその時、空母と戦艦の残骸の間をすり抜けるようにシュトラールの姿が見えて来た。
「後方より未確認機!」
「あれは・・・・」オンドールは思わず身を乗り出した。
「おじさま、私です!バハムートに乗り移ってヴェインを止めます!」通信機からアーシェの声が聞こえて来た。
今まで緊迫していたオンドールの表情が一瞬緩んだが、すぐに厳しい口調になった。「何をおっしゃる!無謀すぎます!殿下の役目は戦後にこそある!」
「このまま負けたら、戦後も何もないでしょう?突入の援護を!」
「いかん!後退なさい!シュトラールを止めろ!!」
「待ってくれ!・・・ま、待って下さい。ラーサー・ソリドールです」
そのとき、通信機からラーサーらしき声が聞こえて来た。
オンドールははっとして耳を傾けた。
「オレも一緒に行くから、安心して下さい!ちゃんとアーシェを守るから!」
「ラーサーだと?そうか、彼を人質に・・・」
オンドールは、おそらくラーサーを人質として連れているのだろう、と即座に判断したのだ。
「いいえ、おじさま、ヴェインと戦うそうです!」
オンドールのの誤解を取り消すようにアーシェが言った。
「オレたちに任せろ!」
ラーサーらしき声が答えた。
シュトラールの中で、ラーサーと名乗って通信機で喋っていたのはヴァンだった。変声機を使って、ラーサーに成り済ましていたのだった。
ヴァン成り済ますラーサーの声を聞いてから、しばらくして、オンドールは重苦しい口調で答えた。
「・・・わかりました。お二人にかけましょう」
アーシェはヴァンと顔を見合わせ、互いに喜びあった。
そんなヴァンを見て、パンネロは呆れた口調で言った。
「ラーサー様は、『オレ』なんて言わないよ」
「そうだっけ?」
とぼけた口調でヴァンが答え、一瞬、緊迫した船内が和やかな雰囲気になった。
「それじゃあ支援砲撃頼む。派手にぶっ放しといてくれ。こっちで間合いを読んで突っ込む!」
バルフレアの声を聞き、オンドールは解放軍達にシュトラール援護の指示を出した。
シュトラールは踊るように砲撃をかいくぐって、ついにバハムートの発着ポートへとすべりこんだ。
ラバナスタ上空では、解放艦隊が、アーシェたちの成功を信じて必死に戦い続けていた。その援護を受け、アーシェたちはついに空中要塞バハムートへと潜入を果たした。バハムートの内部を進む途中にも、ヴァンたちは解放軍からの攻撃で衝撃を感じ、その度に、要塞内は大きく揺れた。その事態に恐れる事もなく、フランが冷静に状況を読んでいた。
「解放軍は善戦してるわ。私たちもしくじれないわね」
「・・・大丈夫。オレたちが勝って、アーシェは女王様だ」
「女王様かぁ。でもなったらなったで大変そうだな」女王に即位したアーシェが遠い存在になってしまう事を惜しむような口調でパンネロが言った。
バッシュはバルフレアに向かって「その時は女王様を誘拐して名をあげたい、空賊の出番さ」と、からかうように言った。彼は、アーシェのバルフレアへの思いに気づいていたのだ。王女に思われ、これからおまえは、どうするつもりなんだい?、と確かめるような言葉だった。
しかし、この時のバルフレアは死を覚悟してバハムートに入っていた。到底、アーシェとの未来どころか、自分の未来についてなど考えることもできなかった。
思いがけずバッシュにアーシェのことをふられ、夫を亡くし、いろいろなことに傷を負って来たアーシェを見つめた。アーシェは、たとえ愛する人が死んでも強く生きていける女だ。そして破魔石を捨てる事が出来た強さがあるのなら、これからも女王として強く生きていけるだろう、と。
「・・・・アーシェなら自力で逃げ切ってみせるだろ?」その思いが、そんな言葉になってアーシェに向けられた。
アーシェはちょっとムっとして、バルフレアの、自分への思いがどこにあるのか試すように言った。「・・・そこまで強いと思っているの?」
バルフレアもアーシェも若すぎて、この時はお互いの本当の弱さに気づくことができなかったのだ。
「別に強くなくてもいいさ」
バルフレアに変わって答えたのはヴァンだった。
「一緒に来たし、一緒に行くんだ」
そうして彼の瞳は、別に強くないかもしれないけど、自分が最も信頼するアーシェが女王になった、平和で静かなダルマスカの未来を見ていた。
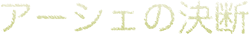

 戦乱の幕開け
戦乱の幕開け ファイナルファンタジー12
ファイナルファンタジー12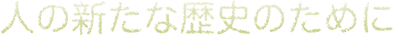
 突撃
突撃
